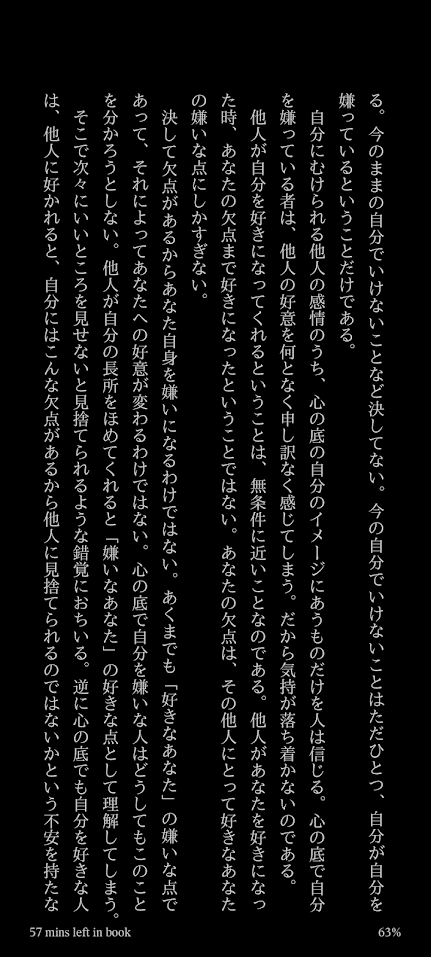今日はTAを終えたあと、新橋のラムちゃんに行った。禁酒中なのに飲み屋!?という感じだが、しっかりウーロン茶しか飲んでないので安心して欲しい。ソフトドリンクを飲んで、「この酒ソフトドリンクみたいに飲みやすいな!」ということで、脳みそを騙している。結構効きます。ジンギスカンは多分2月の北海道旅行ぶりだと思うが、やっぱりおいしいですね。というか肉は心を回復させる。少し気持ちが落ち込んでいて食事が喉を通らなくなりかけていたが、肉を食って回復したような気がする。気持ちが落ち込んでいたのは自分のせいだが……
自分の言葉で相手を傷つけた。なのに自分はその相手に少し苛ついていたのだ。どちらも全く行動原理が分からない。親しい人にしかこのようなミスをしないので今までは謝って再発しないようにしようと思っていた。だが、今回はあまりにひどかった。幸いなことに、今読んでいた本がこの答えのヒントをくれた。以下、めちゃくちゃ長いその本のまとめ。ばーっと書いたので書き損じが多いが、許して欲しい。
少し前に「自分に気づく心理学(愛蔵版)」を読んでいると言っていたが、ついに読み終えて、2周目に入った。この本を一言でまとめると、自分の中にある依存心を認めてそれと向き合うことで幸せになれるよということを述べている。
第1章は、人と接することについて書いてある。他人の目を気にして生きている人は、子供の頃にやさしさに触れられなかった人であって、自分の気持ちを抑圧する傾向にある。何をしても他人の評価が気になる人、誰かに尽くすことが人付き合いで重きをおいている人がこれに当てはまる。子供のころに親に本当のやさしさを貰えなかったことで、自分の認知を曲げて、甘えの気持ちを隠しているから辛いのだというのが筆者の主張だ。自分はここが辛かった。自分は親に甘やかされて生きてきたと思っているし、親は無条件の愛をくれたと思っている。だが、筆者はこれは違うと言う。幼い頃にやさしさに触れない人はやさしさが分からないからこのように考えるらしい。自分がこの状態かどうか、1つ見分け方を考えた。子供の時、お手伝い等をしないと褒められないとか、親を喜ばせよう、失望させないようにしようと考えているとか、こういうことがあったらやさしさに触れていない可能性が高いと思う。
筆者は、この本を通じてこのような心の成長の遅れを持つ人(僕はそう思っている)を神経症的な人間と呼んでいる。
第2章は、第1章でも少し触れられた「甘えの欲求」について書いてある。何かに執着する人、規範意識が強い人、何か仕事をしていないと不安になる人は甘えの欲求を心の奥に抑えてしまっているらしい。自分が心から欲するものがあっても、頭の中にある”こうであるべき”という考えがこれを無意識的に抑圧している。それによって心と行動に矛盾が生まれ、生きるのが辛くなる。気持ちが落ち着かない、イライラする、生きるのが難しい、他人の目が不安である人は、自分を抑圧している人だと筆者は言う。このような人は決まって自分に自信が無い。その人の自信は他人の評価に依存しており、自分の存在が自分自身によって証明されることがないかららしい。幼い頃に甘えの欲求が満たされていれば、何もしていなくても自分の存在が証明されていると感じる。甘えの欲求が満たされなかった人は、自分の行動を意識してしまい、何もしていない自分は無意識であり”なかった”ことになるから不安になる。なので、甘えの欲求を自覚することによって、これを満たす必要がある。そうすれば自分が生きていても良いのだと思えるようになっていき、自身が生まれ、依存心が少なくなる。自分はここも辛かった。本には甘えの欲求は隠されているため当人には見えないみたいなことが書いてある。じゃあ詰んでるじゃん!と叫んでしまった。しかも、甘えの欲求は自分にとって気が引ける行為らしい。甘えの欲求を満たすことが重要であることは分かったのだが、それが相当難しいことだと感じる。大人ならこの対応策がわかるはずでしょ?というのが筆者の意見らしいし、僕もそれは正しいと思う。時間をかけて頑張ろうと思う。
第3章は、不安についてより詳しく書かれている。不安な人は、他人に干渉されない世界を持っていない。逆に、安心感というのは他人に干渉されない世界を持つ。神経症的な人間は自信の無い自分が他人に見られていると感じ、自分を重要性を誇示しようとする。自分の優れているところをアピールするのが、この行動に当たる。そもそも自分の世界が見られると感じること自体が普通の人にはない。だが、神経症的な人間はこれがあり、これによって攻撃的になる。自信が無いから過剰防衛するのだ。つまり、劣等感を感じているのだ。このような人は他人に向けた怒りが分からない。親が所有欲の強いと、このようなことが起きやすい。親に気に入られるように行動するのが当たり前とすり込まれ、少し理不尽な事でも怒りを表さずそれを遂行する。また、これの延長線として、怒りの感情に罪悪感を覚える。親や同胞に向かって怒りの感情が生まれることが受け入れられない。だが、自分の中の怒りや敵意に気がつくことで、自分と他人からの自分の評価を切り分けられるかもしれない。親だからといって、怒りや敵意を持ってはいけないということはない。自分的には、この章は自分と若干ズレているように感じた。だけど、合致していそうな部分もあった。自分はとにかく他人に気に入られよう、見捨てられないようにしようとしている。これが普通ではないのか、と衝撃であった。
第4章は、イライラしやすい人についてだった。予定が少しズレるとイライラするとか、そういうことである。全てが自分の思い通りにならないとイライラするのだ。だが、それはその物事が間違っているのでは無く、生き方全体が間違っているというのが筆者の主張だ。思い通りにならないことにイライラするのは、小さい子供と同じだ。小さな子供は自分勝手な要求をし、これが満足されないと怒る。大人でこのような状態にある人は、神経症的な人間である。この人は、子供の時にこのような自分勝手な振る舞いが許されなかった。甘えの欲求が満たされなかった。だから、大人になってもこれを求めている。だが、ストレートに甘えを表現することが恥ずかしいことだとして、自分にも相手にもこの気持ちを隠す。その上、イライラしている原因を合理化して他人にぶつける。このようなイライラにマトモに対処しようとしても、解決しない。なぜなら、本人も欲求が見えていないので、本人にとってもなんで怒っているのかわからないからである。何か原因もわからず不愉快になったら、自分の中に隠された欲求があると疑うのが解決に繋がる。実はこの章には他に例があるのだが、上手く説明できなさそうなので割愛。この他の例が大事なのだが、長くなるよりかはいいかな……僕は結構イライラしやすい人だ。ただ、この章に関しては大分マシになった。怒ることはエネルギーを使うので、ずっと怒らないように努めてきた。これで逆に自分の怒りに気付きにくくなったが、この章で言うような欲求は見える。「自分はこうしたかったけどできなくなったからイライラしているんだ」とわかる。まあこれを押し殺して何もなかったようにしているから第2章や第3章の内容がより深刻になっているのかもしれないが。
第5章は、人を愛する、人に愛されることについて。ここの章は難しかった。前章までの問題が解決して初めて見える世界について話されているように感じた。ただ、自分が愛だと思っていることが実はそうでもないということはわかった。今まで恋愛や友人関係で違和感を覚えていたことの答えの1つな気がする。が、そうするとこれまでのは何だったのか、虚無感に襲われる。ここの章は、文書の1つ1つは理解できても全体としてよく分からなかったので、筆者の言葉をいくつか引用する。
・他人があなたを好きになった時、あなたの欠点まで好きになったということではないし、欠点があるからあなた自身を嫌いになるわけではない。
・好かれているということは、相手にことさら何もしてあげる必要はない
・役に立たなければ相手の好意をひきつづき保てないと思っていることが間違いなのである
・神経症気味な人というのは、今眼の前にいる人を理解しようとすることより先に、その人からわるく思われないようにしようという防衛的姿勢がさきにたってしまう。
・親密な関係においては、相手が自分と直接関係の無い世界で幸せであることを喜ぶものである。ところが共生的関係(加筆:共生的関係とは、虚勢を張ったり迎合したりして普通にしていられない関係)においては、自分と直接関係のない世界で幸せであることは許されない。
・真実の愛は間接的に示される
最後のところだけ、少し補足を。直接的に表されるやさしさ(?)は、やさしさを与えている人の自己満足であることが多いということで、間接的に表されるやさしさこそが本物のやさしさであるということだ。直接的なものとして、例えばバッグを持ってあげることや旅行に連れて行ってあげることがあげられる。間接的なものとして、例えば何か欲しいものがあると聞いたとき、忙しい中でもそれを忘れずに、タイミングを見つけて探すことがあげられる。言われてみれば当たり前ではあるが、こんな当たり前なことにも全然気付いていなかった。優しい人間であろうとずっと思っていた。なので色々な人に、彼らが欲しているであろうことをしてきた。結果としてただの便利人間になってしまった。役に立たなければ相手の好意をひきつづき保てないと思っているのでこれで良いとまで思っていた。確かにこれは自己満足だったのかもしれない。
第6章は、多分自分の感情の重要性についてだと思う。後半になるにつれて自分の幼稚的な心では何を言っているのか分からなかった。ただ、自分の自然の感情をなくしてはいけない、自分はこう思う筈であるという考えは恐ろしいことだ、と言っていることは分かった。自分の自然の感情を無くすことで生きることへの無意味感が増大していく。自分自身の感情というものが薄れ、こうであるべきだろうという感情に流される。本では、この原因が情緒的に未成熟な親のせいだと言っている。親が、このように感じるべきだということを言うことで、子供はそれを感じざるを得ない。子供は親無しでは生きていけないので、これに逆らうことは死ぬくらい怖いことに感じる。そのため、どんな感情も恐怖によって生み出されることになる。この恐怖は殺される恐怖であると著者は言う。なので、他の感情はこの恐怖に圧倒される。ただ、この恐怖を感じなくなる時がある。エネルギーを使い切った時である。この時が、ただ無気力で、肉体が息をしているだけの状態である。これがうつだ。うつ病になる前に、自分の本当の感情に耳を傾けることが重要だ。また、自分の持つ「立派な自分」や「良い自分」のイメージは捨てなければならない。このイメージはあくまでイメージなので、本物ではない。このイメージはただ自分の弱さを合理化しているだけらしい。このイメージに沿って生きるのは自分自身ではないから、自分の選択・気持ち・行動を持つべきだということだろう。僕にはこうまとめるのが限界だ。確かに、自分はこうであるべきだという像を持っている。それは時には賞賛され時には自分のメリットになる。しかし、確かに自分がやりたいことでは無かったかもしれない。他人にどう見られるかしか考えていない像だったと反省した。ただ、それ以外の生き方を知らないから、このイメージを捨てるのは僕にはとても難しそうだ。ただ、こうあるべきと思う自分を演じる中で辛いと思ったり寂しいと思ったりすることはあったように思う。こういう気持ちを無視しないことが自分の感情に気付く一歩なのかもしれない。年をとるにつれ、自分の感情がよく分からなくなっていた。自然なことかと思っていた。だが、友達がある嬉しい出来事に対して涙を流したのを見て、涙を流すほど感情が動くことに驚いた。自分に嬉しくて泣くという出来事があるのか、しばらく考えて、思いつかず諦めた。感情がある世界はどんなに生きている気がするのだろうか。
第7章は、自分を大事にしろ、という章だ。自分の気持ちを大事にして、自分の幼稚性や抑圧された部分を認めることが大事だと。自分の言葉が相手にどう受け止められるかずっと考えるのは思いやりのない事で、相手のことを思っていれば自分の言葉が相手にどう受け止められているかわかると。他人に好かれるとき、その相手はそれを喜びとして受け取り、決して心の負担にはなっていないのだと。そういうことが書かれている。依存する心が残っているとき、自分のことばかり考えてしまうことになる。なので、他人の好意に気付かない。好意に気付けず愛に飢え、他人からよく思ってもらうために心をすり減らす。逆に、自分は愛されないと決めつけず、自分は生きるに値する存在だと決断する必要がある。
・日常生活で自分にやさしくすること、日常生活で自分をよく世話すること、日常生活で自分が自分に甘えることを許すこと、日常生活で自分のめんどうをよく見ることを忘れないことである。
自分を大事に、自分にやさしくすることが神経症的な人間から脱却する方法であるとこの本は締めくくっている。自分で自分を満たして初めて他人の本当の好意に気がつく、また、自分を認めて初めて他人に対して本当の愛を与えられるようだ。
この本を読んで、知人からの言葉のいくつかを初めて理解した。自分のことは自分が一番わかっていると思っていたが、みんなの方がよくわかっているのかもしれない。自分の今までの行動に反省すべき点がとても多くあった。そして改めて自分の心の幼稚さを実感した。